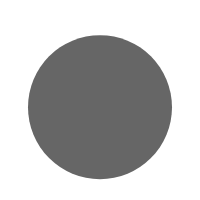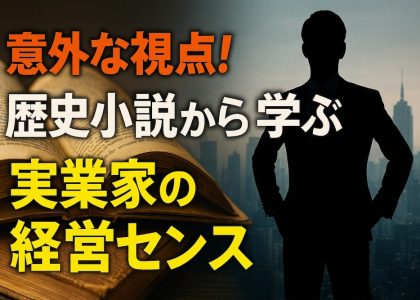私が品質保証部門で働き始めて15年以上が経ちました。
その中で最も印象深く、私の品質管理に対する考え方を根本から変えた出来事があります。
入社直後に担当したバリデーション業務で発生した重大な逸脱対応でした。
当時の上司だった元PMDA査察官から言われた「バリデーションは製品と患者を守る防波堤」という言葉が、今でも私の業務の根底にあります。
この記事では、現場で実際に経験した逸脱事例を通じて、バリデーションが果たす本質的な役割と、現場レベルで実践できる具体的なノウハウをお伝えします。
あなたが日々直面しているバリデーション業務の課題や、「なぜこんなに細かく検証する必要があるのか」という疑問に、実務経験に基づいて答えていきます。
GMPの観点から見たバリデーションの意義を理解し、監査・査察にも自信を持って臨める知識と実践力を身につけることで、製品品質の向上と患者安全の確保に貢献できるようになるでしょう。
目次
バリデーションの本質:なぜそれが製品と患者を守るのか
GMPにおけるバリデーションの定義と役割
厚生労働省のGMP省令第2条第13号では、バリデーションを「製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすること」と定義しています[1]。
しかし、この定義だけでは現場の技術者にとって、なぜそこまで厳格な検証が必要なのかが見えてこないかもしれません。
私が現場で15年以上バリデーション業務に携わってきた経験から言えるのは、バリデーションとは単なる書類作成作業ではなく、製品品質を恒常的に保証するための科学的証明プロセスだということです。
医薬品は患者さんの命に直結する製品です。
製造プロセスの各ステップが設計通りに機能し、規格を満たした製品を毎回確実に製造できることを事前に証明しておかなければ、患者さんに安全な薬をお届けすることはできません。
この「事前の証明」こそがバリデーションの本質であり、GMPの三原則である「人為的ミスの防止」「汚染および交叉汚染の防止」「品質の保証」を実現するための具体的な手段なのです[1]。
「逸脱」と「潜在リスク」のつながり
現場でよくあるのは、「バリデーション済みの設備だから大丈夫」と考えてしまうことです。
しかし、実際にはバリデーション後も様々な要因で逸脱が発生し、その度に製品品質への影響を評価する必要があります。
GMP省令第15条に定められた逸脱とは、「製造手順等からの逸脱」を指し、定められた作業手順や管理基準から乖離している状況や状態のことです[2]。
逸脱が発生した際の対応プロセスでは、まず発生部門による評価と記録作成、品質部門への文書による報告、そして品質部門による確認という一連の流れが求められます[2]。
重要なのは、逸脱を単なるトラブルとして処理するのではなく、潜在的な品質リスクの顕在化として捉え、システム全体の改善機会として活用することです。
実際に私が経験した事例では、製造設備の温度管理で微細な逸脱が発生しましたが、その根本原因を追究することで、バリデーション時には想定していなかった環境要因の影響を発見できました。
品質保証部門の責任と視点
品質保証部門の役割は、単に逸脱報告を受けて承認することではありません。
製造現場と規制要求の間に立ち、科学的根拠に基づいて品質判定を行う「ゲートキーパー」としての機能を果たすことが求められます。
現場で実感するのは、逸脱管理と変更管理がGMP管理レベルを判断する重要な指標になっているということです[2]。
通常の定められた手順に従った作業から、何らかの変更や予期せぬ逸脱が発生した時の対応こそが、その製造所の品質システムの真価を問われる場面なのです。
私たち品質保証部門は、製造部門の判断だけに委ねることなく、独立した立場から品質への影響を評価し、必要に応じてCAPA(是正措置・予防措置)の実施を求める責任があります。
この責任を全うすることで、製品と患者を守る最後の砦としての役割を果たすことができるのです。
実例から学ぶ:逸脱事例に見るバリデーションの盲点
逸脱が発生した背景とその原因分析
私が入社2年目に経験した事例をお話しします。
ある固形製剤の製造ラインで、打錠工程において錠剤硬度の規格逸脱が3ロット連続で発生しました。
当初は「たまたまの製造トラブル」として処理されそうになりましたが、品質保証部門として詳細な原因調査を実施したところ、バリデーション時には見過ごされていた重大な盲点が明らかになったのです。
原因は、打錠機の圧縮力制御システムと製造環境の湿度変化の相互作用にありました。
バリデーション時は標準的な環境条件(温度20-25℃、湿度45-65%)で実施していましたが、実際の製造時期は梅雨期にあたり、湿度が上限値近くで推移していました。
原料の吸湿性が想定以上に高く、これが圧縮力の設定値に微妙な影響を与えていたのです。
この事例から学んだのは、バリデーション時の試験条件と実製造時の環境条件の差が、予想以上に大きな影響を与える可能性があるということです。
逸脱対応のプロセスとその難しさ
逸脱対応で最も困難なのは、「重大な逸脱」かどうかの判断です。
GMP省令では重大な逸脱の場合の対応について規定していますが、その判断は製造所で行うべきとされています[2]。
前述の硬度逸脱事例では、初期段階では「軽微な逸脱」として扱われる予定でした。
しかし、品質保証部門として以下の観点から総合的に評価した結果、重大な逸脱として分類することを決定しました。
評価のポイントは、逸脱の再現性、患者への潜在的影響、製造プロセスの予測可能性への影響でした。
3ロット連続という再現性の高さは、システマティックな問題の存在を示唆していました。
また、錠剤硬度は服用時の崩壊性や薬物溶出に直結するため、患者さんへの影響も考慮する必要がありました。
最も重要だったのは、バリデーション済みプロセスの予測可能性が損なわれているという事実でした。
この判断により、単なる製造調整では済まず、バリデーションの見直しまで含めた包括的な対応が必要となりました。
現場で見落とされがちなポイント
ユーザー要求仕様書(URS)の曖昧さ
現場でよくあるのは、URS(ユーザー要求仕様書)の記載が曖昧で、実際の運用時に解釈の違いが生じることです。
前述の事例では、打錠機の環境条件に対する制御要求が「JIS標準環境条件下での動作保証」という記載にとどまっていました。
実際の製造現場では、季節変動や日内変動を考慮した幅広い環境条件での安定動作が求められます。
URSを作成する際は、以下の点を具体的に明記することが重要です:
動作保証環境範囲(温度・湿度の最大変動幅)、原料物性の変動範囲(水分値、粒度分布等)、連続運転時間と停止・再開時の制御要件、異常時の検知・警報・停止の基準値設定などです。
再現性試験とOQ評価の境界
OQ(運転時適格性評価)では、設備が予期した運転範囲で意図したように作動することを確認します[3]。
しかし、現場では「何回繰り返せば再現性が確認できたと言えるのか」という判断に迷うことが多々あります。
私の経験では、最低3回の繰り返し試験は必須ですが、重要なのは回数よりも試験条件の設定方法です。
最適条件での1回、上限・下限条件での各1回、そして中間条件での1回以上という組み合わせで、プロセスロバストネスを確認することを推奨します。
SOPと実作業の乖離
バリデーション時に作成したSOPと、実際の作業手順の間に乖離が生じることも頻繁にあります。
特に、作業者の習熟度向上や効率化の観点から、現場独自の工夫が加えられることがあります。
これらの変更が文書化されていないと、いざという時に原因追究が困難になります。
定期的なSOP遵守状況の確認と、必要に応じた変更管理の実施が不可欠です。
現場の作業者との定期的なコミュニケーションを通じて、実際の作業状況を把握し、SOPの実用性を継続的に評価することが重要です。
現場で実現するバリデーション:教訓を活かす実践ノウハウ
バリデーション計画の立て方とリスク評価
逸脱事例の経験を踏まえ、私たちの部門ではリスクベースアプローチを中心としたバリデーション計画の策定方法を確立しました。
まず最初に実施するのは、製品のCQA(重要品質特性)の特定と、それに影響を与える可能性のあるプロセスパラメータの洗い出しです。
前述の硬度逸脱事例を受けて、環境条件の変動を重要なリスク要因として位置づけ、季節変動を考慮した試験設計を標準化しました。
具体的には、年間を通じた環境条件の実測データを3年分収集し、その変動範囲をバリデーション試験の条件設定に反映させています。
リスク評価では、ICH Q9の品質リスクマネジメントの考え方を活用し、影響度と発生頻度のマトリックスでリスクレベルを分類します[3]。
高リスクと判定された項目については、より詳細な検証を行い、中・低リスク項目については効率的な確認方法を選択することで、限られたリソースを有効活用しています。
IQ/OQ/PQ文書の見直しとトレーサビリティの確保
適格性評価の各段階で重要なのは、次の段階への橋渡しとなる情報の整理と文書化です。
IQ(据付時適格性評価)では、設備が要求仕様に基づいて正しく納品・設置されたことを確認しますが、単なるチェックリストの確認に終わらせてはいけません[3]。
設置状況の写真撮影、主要部品のシリアル番号記録、校正証明書の確認といった、後の段階で参照が必要となる情報を体系的に整理しています。
OQ(運転時適格性評価)では、前述した環境条件変動を考慮した試験設計を実装しています。
標準条件での基本機能確認に加え、想定される最大変動条件での性能確認を必須項目としています。
PQ(性能適格性評価)では、実製造条件に可能な限り近い状態での検証を心がけています。
私たちの部門では、実際の製造スケジュールに合わせた連続運転試験や、製造作業者による実作業での性能確認を含めた総合的な評価を実施しています。
複雑なバリデーション業務においては、日本バリデーションテクノロジーズ株式会社などの専門企業が提供する技術サポートやコンサルティングサービスを活用することも、効率的な品質保証システム構築の有効な手段となります。
教育訓練と「作業者の納得感」を得る工夫
バリデーションの成功は、関係者全員がその意義を理解し、積極的に参加することにかかっています。
特に製造現場の作業者の方々には、「なぜこのような詳細な検証が必要なのか」を理解していただくことが重要です。
私が心がけているのは、患者さんへの影響という観点から、バリデーションの意義を説明することです。
「この工程で品質に問題が生じた場合、最終的に薬を服用される患者さんにどのような影響があるか」を具体的に示すことで、作業者の方々の当事者意識を高めています。
また、バリデーション結果の共有も重要な要素です。
検証によって確認できた安全余裕度や、想定リスクに対する対策の有効性を数値やグラフで示すことで、作業者の方々に安心感と誇りを持って作業に取り組んでいただけるようになります。
定期的な振り返り会議では、現場からの改善提案も積極的に取り入れ、継続的な改善サイクルを回しています。
逸脱発生時の初動と記録対応のコツ
逸脱が発生した際の初動対応は、その後の調査の質を大きく左右します。
最も重要なのは、発生状況の正確な記録と、関連する全ての情報の保全です。
私たちの部門では、逸脱発生時の標準的な初動チェックリストを作成し、製造現場と共有しています。
発生日時の正確な記録、発生時の環境条件(温度・湿度・気圧等)、使用していた原料・資材のロット情報、作業者の特定と作業状況の聞き取り、関連する製造記録・試験記録の保全、影響範囲の暫定評価(同一ロット内、前後ロットへの影響可能性)といった項目を体系的に整理します。
記録作成では、客観的事実と推測・解釈を明確に分けることを徹底しています。
「○○のようだった」「○○かもしれない」といった曖昧な表現は避け、測定可能な数値や観察可能な現象として記録することで、後の原因調査の精度を高めています。
また、写真や動画による記録も積極的に活用し、文字だけでは伝えきれない情報の保全に努めています。
規制と実務の橋渡し:ガイドラインを現場でどう活かすか
ICH Q8/Q9/Q10とPIC/Sガイドラインの実務応用
国際的なガイドラインを現場レベルで活用する際に重要なのは、理念の理解と具体的手法の両立です。
ICH Q8(製剤開発)、Q9(品質リスクマネジメント)、Q10(医薬品品質システム)の「Qトリオ」は、リスク及び科学に基づく医薬品品質への新たなアプローチを提唱しています[3]。
私たちの部門では、これらのガイドラインを以下のように実務に適用しています。
Q8の製剤開発アプローチでは、QbD(Quality by Design)の考え方を取り入れ、目標製品品質プロファイル(QTPP)の設定から始めて、重要品質特性(CQA)と重要工程パラメータ(CPP)の特定を体系的に行っています。
前述の硬度逸脱事例でも、このアプローチにより環境要因の影響を事前に特定できていれば防げた可能性があります。
Q9の品質リスクマネジメントでは、FMEA(故障モード影響解析)やHAZOP(ハザード・運転解析)などの手法を活用し、潜在的リスクの洗い出しと評価を定期的に実施しています。
Q10の医薬品品質システムは、経営陣のコミットメントから現場の日常業務まで、品質保証の仕組みを包括的に構築するための指針として活用しています。
PIC/S GMPガイドラインについては、日本が2014年に加盟して以降、国際的な査察基準への対応が求められています[4]。
特にサイトマスターファイルの作成・維持や、サプライヤー管理の強化は、従来の国内GMP対応では不十分な部分でした。
査察で見られる「バリデーションの真価」
PMDA、FDA、EMAなどの査察では、バリデーション文書の内容よりも、その背景にある考え方と実際の運用状況が重視されます。
私が経験した査察では、以下のような点について詳細な質問を受けました。
バリデーション時の判定基準設定の根拠、実製造時とバリデーション時の条件差異とその評価、逸脱発生時の対応プロセスの実効性、継続的改善の取り組み状況といった項目です。
査察官が最も注目するのは、形式的な文書の完備度ではなく、科学的根拠に基づく判断プロセスと、それを支える組織的な取り組みです。
特に重要なのは、トップマネジメントから現場作業者まで、バリデーションの意義と重要性について共通の理解があるかどうかです。
査察時には、様々な階層の担当者に対して質問が行われるため、組織全体での知識共有と意識統一が不可欠です。
海外査察対応から得た視点と改善例
FDA査察を受けた際に指摘された重要なポイントの一つが、データインテグリティ(データの完全性)の確保でした。
バリデーション記録において、生データの管理、電子記録の監査証跡、変更履歴の追跡可能性などについて、厳格な管理が求められます。
この指摘を受けて、私たちの部門では以下の改善を実施しました。
電子記録システムの監査証跡機能の強化、紙記録のスキャン・保管プロセスの標準化、データバックアップ・復旧手順の文書化と定期テスト、アクセス権限管理の見直しと定期監査といった対策を講じました。
また、査察対応で学んだ重要な教訓は、「説明可能性」の確保です。
どのような判断にも科学的根拠と合理的理由があり、それを第三者に分かりやすく説明できることが求められます。
バリデーション計画書や報告書の記載においても、この観点を常に意識し、判断の根拠と理由を明確に記述するよう改善しました。
海外査察の経験を通じて実感したのは、日本の製薬業界の技術的水準の高さと、それを適切に文書化・説明する能力の重要性です。
優れた技術と品質管理を行っていても、それが適切に伝わらなければ評価されません。
グローバルスタンダードに対応するためには、技術的な実力と国際的なコミュニケーション能力の両方が必要だということを、強く感じています。
まとめ
バリデーションが果たす本質的な役割の再確認
この記事を通じてお伝えしたかったのは、バリデーションが単なる規制要求への対応ではなく、製品品質の恒常的確保と患者安全の保証という、私たち製薬業界の根本的使命を果たすための重要な手段だということです。
私が経験した逸脱事例は、バリデーション時の想定不足が実製造時の品質問題につながる可能性を示していました。
しかし同時に、適切な逸脱管理プロセスを通じて、システムの改善と品質向上を実現できることも証明されました。
GMPの観点から見ると、バリデーションは製造プロセスの予測可能性と再現性を科学的に証明する活動です。
これにより、「誰がいつ作業しても、必ず同じ品質・高い品質の製品を作る仕組み」を構築し、患者さんに安全で有効な医薬品をお届けすることができるのです。
現場の失敗から学び、再発を防ぐために
失敗や逸脱は避けられないものですが、それらから学び、システム全体の改善につなげることが重要です。
私たちの経験から得られた教訓をまとめると、以下のようになります。
バリデーション計画では、実製造環境の変動要因を十分に考慮する必要があります。
IQ/OQ/PQの各段階で、次の段階に必要な情報を体系的に整理し、トレーサビリティを確保することが重要です。
教育訓練では、患者さんへの影響という観点からバリデーションの意義を説明し、関係者全員の理解と協力を得ることが必要です。
逸脱発生時は、客観的事実の正確な記録と、科学的根拠に基づく影響評価を迅速に実施することが求められます。
国際的なガイドラインの活用では、理念の理解と具体的手法の実装を両立させ、査察時の説明可能性を確保することが大切です。
「現場で実現可能なGMP」を目指すあなたへのメッセージ
私がこの記事で最もお伝えしたいのは、理想と現実のバランスを取りながら、実務レベルで実現可能な品質保証システムを構築することの重要性です。
規制要求を満たすことは当然ですが、それが現場の負担になりすぎて持続不可能になっては本末転倒です。
現場の実情を理解し、作業者の方々と一緒に改善を進めていくことで、真に実効性のあるバリデーションシステムを作り上げることができます。
あなたがバリデーション業務で直面している課題は、決して特別なものではありません。
多くの技術者が同様の困難を経験し、それを乗り越えて成長してきました。
重要なのは、一つひとつの経験から学び、それを次の改善につなげていく継続的な取り組みです。
バリデーションを通じて製品品質を向上させ、患者さんの安全と健康に貢献するという私たちの使命を、現場レベルで着実に実現していきましょう。
そのための知識と経験を積み重ね、製薬業界全体の品質向上に寄与できる技術者として成長していかれることを心から願っています。
参考文献
[1] 厚生労働省 GMP省令・バリデーション基準 – 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令とバリデーション基準 [2] GMP Platform – 医薬品GMP理解の第一歩(逸脱管理) – 逸脱管理の核心的要素と対応プロセスの詳細解説 [3] 日本製薬工業協会 ICH Q8、Q9、Q10ガイドライン運用実務研修会 – リスク及び科学に基づく医薬品品質への新たなアプローチの実務応用最終更新日 2026年2月7日 by landru